マイコプラズマのすべて ~その2、症状・診断・治療編~
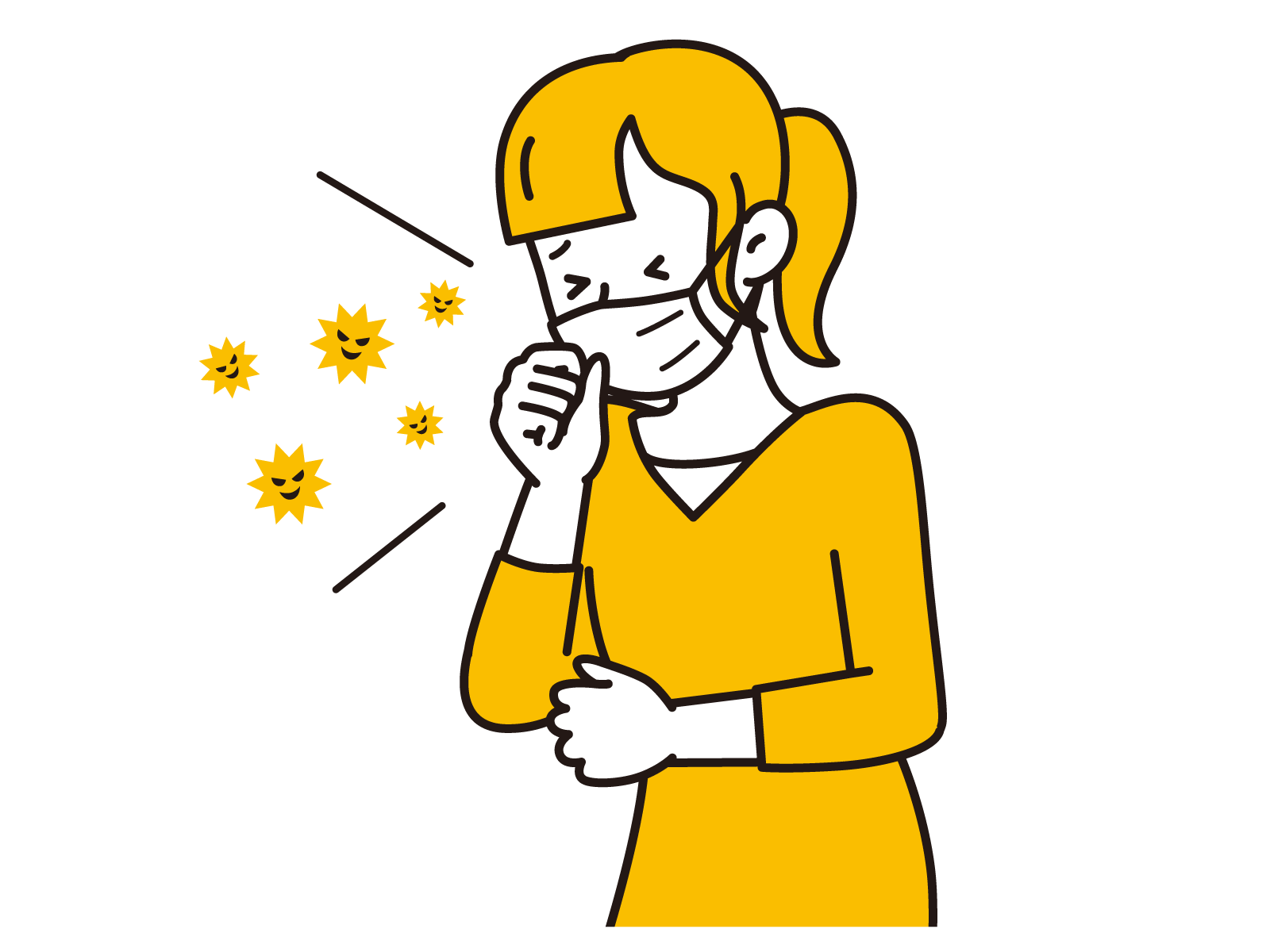
目次
- 潜伏期間
- マイコプラズマによる急性上気道炎の経過
- マイコプラズマによる肺炎の経過
- マイコプラズマの直接的な診断方法(PCR検査)
- マイコプラズマの直接的な診断方法(抗原検査)
- マイコプラズマの直接的な診断方法(培養検査・抗体検査)
- マイコプラズマの間接的な診断方法(流行状況や症候からの推定)
- マイコプラズマの治療
1.潜伏期間
多くの感染症では、微生物に感染してから症状が出るまでの間に一定の時間がかかります。これを潜伏期間と呼びます。
例えばインフルエンザの潜伏期間は1~3日、新型コロナウイルスの潜伏期間は2~7日(多くは2~3日)です。
当然マイコプラズマにも潜伏期間がありますが、これが意外と長く2~3週間もあります。
このためマイコプラズマ感染症では、患者さんがどこから菌をもらったのか覚えていない(あるいは直近に会った人から菌をもらったと勘違いしている)ことがよくあります。
2.マイコプラズマによる急性上気道炎の経過
マイコプラズマはウイルスと細菌の両方の特徴を持つ微生物です。なのでウイルスの特徴が強く出た場合と、細菌の特徴が強く出た場合とでは異なる経過をたどります。
まずマイコプラズマのウイルスとしての特徴が強く出た場合の経過を見てみましょう。
前編で説明したように、ウイルスは上気道の複数臓器、つまり鼻、喉、気管に感染します。マイコプラズマも同様にこれらの臓器に感染し、上気道炎を起こします。
この場合の症状は発熱、鼻水、咽頭痛、咳です。ただしマイコプラズマは気管よりも奥で増殖しやすい菌ですので、鼻水は軽度か無いことが多いとされています。また咽頭痛は咽頭と気管の距離が近いこともあってか良く見られますが、痛みの程度は軽いことが大半です。
咳は概ね発症3日後くらいから強くなります。教科書的には痰は少ないとされていますが、問診をすると少量の痰の訴えがあることも多くあります。
熱や咽頭痛は数日で改善し、しだいに症状は咳が中心となります。この咳も対症療法薬で様子を見ているうちに徐々に収まっていきます(特に抗生物質を使わなくても自然と治ります)。
マイコプラズマに感染された方のうち、9割の方はこのような上気道炎の経過を辿ると考えられています。
さて、このようなマイコプラズマによる急性上気道炎と普通の風邪とを症状だけから見分けることは可能でしょうか?
私の結論として、これは不可能です。
このような経過は「咳が強めのウイルス性上気道炎=風邪」と全く同じです。また、特別な治療をしなくても自然と良くなる訳ですから、無理に風邪と分ける必要もありません。
実際に多くの場合、上気道炎の経過を辿る場合にはマイコプラズマと確定診断されることはなく、医者も患者もマイコプラズマであったことは分からないことが大半です。
重要なのは、マイコプラズマの流行期に風邪類似の症状で来られた方の中から、次に述べる肺炎の方を見逃さないことになります。
3.マイコプラズマによる肺炎の経過
マイコプラズマの細菌としての特徴が強く出ると、上気道だけでなく肺にも感染を起こします。
マイコプラズマに感染された方のうち、肺炎になる人は全体の10%程度です。
多くの場合、まず上気道炎の症状が出現してから、数日かけて肺炎らしい症状が見られるようになります。ですので初期の症状はマイコプラズマによる上気道炎と同様に発熱、軽度の咽頭痛、咳になります。
肺炎症例での発熱は38℃以上の高熱が持続することが多いのですが、中には微熱のみという方もおられます。困ったことに熱のみで肺炎かどうかを判断することは出来ません。
咳はしだいに悪化し、夜も眠れなくなることがあります。このような強い咳はマイコプラズマ肺炎の特徴の一つです。初期は空咳が多いのですが、徐々に痰の訴えが見られるようになることもあります。
咳の悪化に伴い喘息のようなヒューヒューといった音が聞かれることもあります(喘息様気管支炎と言って40%程度に見られる所見です)。
その他、耳の痛み、下痢や嘔気などのお腹の症状、胸痛、皮疹などが見られることがあります。特に胸痛は25%程度、皮疹(典型的には多形紅斑)は6~17%(報告によって差が大きい)と比較的高率にみられます。
また、稀な合併症としては中耳炎、無菌性髄膜炎、脳炎、肝炎、膵炎、溶血性貧血、心筋炎、関節炎、ギラン・バレー症候群などが知られています。
このように合併症を並べると怖い感染症のように感じる方もおられるかもしれませんが、有効な抗生剤が投与されると概ね48時間以内に解熱し、その他の症状も改善に向かうことが大半です。それほど神経質になる必要性はありません。
ただし咳は解熱後も2~3週間に渡り長期に持続することがあります。
マイコプラズマの流行期に熱が長引いたり咳が強い方を見かけた際には、積極的にレントゲン検査を行って肺炎がないかを調べることが重要です。マイコプラズマ肺炎を疑う初見についてはこの後「7.マイコプラズマの間接的な診断法」でも解説しています。
4.マイコプラズマの直接的な診断方法(PCR検査)
マイコプラズマを診断するにあたっては菌の存在を証明する直接的な診断法(単独の検査結果から診断する方法)と、状況証拠を積み重ねることで感染を推定する間接的な診断法(複数の検査結果や所見から診断する方法)とがあります。
まずは直接的な診断方法としてPCR検査についてその利点と限界を解説していきたいと思います。
マイコプラズマの検査の中で、現時点で最も精度が高い方法がPCR検査です。
PCRとは本来、ある特定のDNA配列をたくさん複製する方法です。しかしこれを応用すると、ある微生物に固有のDNA配列が検体にどの程度存在するか(あるいは存在しないか)を調べることができます。RT-PCR法と呼ばれるこの方法は、現在では感染症の診断に広く利用されています。
RT-PCR法は信頼性が高く応用も効きやすいという利点があり、研究室レベルで実施するには最適な方法です。しかし手順が煩雑かつ時間がかかるという欠点があるため、臨床現場で利用するには負担が大きいという問題点がありました。そこでより簡便にPCR検査を行う方法として、LAMP法やQプローブ法といったいくつかの方法が開発されました。
このうち、Qプローブ法は診断と同時にマクロライド耐性菌を調べることが出来るため、非常に有用な検査です。ただし実施できる検査機関・医療機関は限られています。当院では2024年11月29日から、こちらの検査が院内で実施可能となっています。
マイコプラズマを対象にしたPCR検査の手順を説明すると、①口から挿入した綿棒で喉の奥を拭い、②拭い液を化学的に処理した後、③専用の機械にかけることで感染の有無を診断します。当院で購入した検査機器では、③の段階で20~40分ほど(平均30分)かかります。少し時間はかかりますが、当日中に判定が可能です。
一方でPCR検査にも限界があります。それはマイコプラズマは咽頭や鼻腔などの検体を取りやすい場所には少数しか感染しておらず、菌を採取してくることが難しいという点です。
前述のようにマイコプラズマの増殖は鼻や喉よりも気管で活発です。本来喉にはあまり菌はおらず、咽頭にいる菌の多くは咳とともに気管から弾き飛ばされてきたものです。
このため、咳が激しく出ていない感染初期においては、喉から検体をとっても上手く検出できない(偽陰性となる)ことが多くあります。少しでも精度を上げるため、PCR検査に際しては出来るだけ咽頭の奥側から検体を取ることが推奨されています(患者さんにとっては苦しいと思いますが・・・)。
5.マイコプラズマの直接的な診断方法(抗原検査)
次に抗原検査の特徴を見ていきましょう。抗原検査はある微生物に固有のタンパク質の存在を調べる検査です。そのタンパク質が(ある一定量以上)存在していれば陽性、なければ陰性になります。特殊な機械が必要ないため、多くの医療機関で広く実施されています。
マイコプラズマを対象にした抗原検査の手順を説明すると、①口から挿入した綿棒で喉の奥を拭い、②拭い液を試薬と十分に混ぜた後、③混合液を専用のキットに垂らすことで感染の有無を診断します。PCR検査と似ていますが、②の手順が簡単かつ③で特殊な機器が不要であるため、実際はかなり簡便な検査となっています。
ただし、抗原検査の精度はPCR検査より劣ります。
抗原検査キットの一つであるリボテストとQプローブ法とを比較した報告によると、陽性反応一致率は47.4%、陰性一致率は76.9%となっています。これとは別にリボテストの添付文書に記載のRT-PCR法との比較では陽性反応一致率57.1%、陰性反応一致率92.2%です。これらを見ると、PCRで診断できるマイコプラズマ肺炎のうち、半数近くが抗原検査では見逃されることになります。よって少なくとも流行期においては、抗原検査陰性であってもマイコプラズマを否定することは困難です。
さらに抗原検査も咽頭から検体をとる以上、咳が激しく出ていない感染初期の数日には精度がさらに落ちてしまいます。
陽性である場合はまず感染していると判断しても良いと思いますが、陰性であった場合の判断が難しいのが抗原検査の困ったところです。
6.マイコプラズマの直接的な診断方法(培養検査・抗体検査)
かつてPCR検査や抗原検査が今ほど一般的ではなかった際に実施されていたのが培養検査と抗体検査です。ただし現在ではこの2つの重要性は大きく低下しています。
培養検査もPCRや抗原検査と同様に咽頭から検体をとり、特殊な培地の上で菌を増殖させ、増殖した菌の集団(コロニー)がマイコプラズマかどうかを調べる方法です(実際には赤血球付着試験などを実施します)。ただし培養に1~4週間程度かかること、特殊な培地が必要なこと、培養のための専門設備と技術が必要なことなどから、クリニックではほぼ実施されていません。
ただし培養に成功すれば薬剤感受性試験(どの薬剤が効くのか調べる検査)が実施できるというメリットがあります(感受性が分かった頃には、既に治療は終わっているかもしれませんが)。
直接的な診断法の最後に抗体検査について解説します。
これまでの検査は全てマイコプラズマ菌自体を調べる検査です。一方で抗体はマイコプラズマと戦うために私達の体が作り出すものです。よって抗体検査が調べているのは菌自体ではなく、感染によって生じる私達の体の変化になります。
抗体は血液中に存在していますので、この検査には採血が必要です。また多くの医療機関ではマイコプラズマ抗体は外注検査となります。このため抗体検査の結果が判明するまでには数日かかることが一般的です。
また抗体検査は発症初期に実施してもあまり意味がありません。マイコプラズマに感染してから私達の体が抗体を作り出すまでに時間がかかるためです。抗体の中の初期ロットとでも言うべきIgM抗体は発症1週間後くらいから上昇し、2~3週でピークとなります。さらにIgM抗体の改良版であるIgG抗体は発症2週間後くらいから上昇し、3~4週でピークとなります。
このため、特にIgG抗体の値で感染の有無を判断する際には、通常は1回目の採血から2週間ほど間隔をあけてもう1回採血し、この2回の間でIgG抗体がどれだけ増えたかで感染の有無を判定します(通常は4倍以上を陽性とします)。
しかし実際にはこれほど治療開始を待てないため、抗体で診断してから治療を開始するというのは現実的ではありません。
7.マイコプラズマの間接的な診断方法(流行状況や症候からの推定)
直接的な診断法として取り上げた検査のどれも、特に感染初期における診断力が高くありません。
このため、臨床現場ではこれまでに取り上げた検査に頼らずに診断する方法が編み出されています。
流行状況とマイコプラズマ肺炎によく見られる症状を組み合わせて診断するものです。
もともとマイコプラズマは細菌とウイルス両方の特徴を持つため、一般的な細菌性肺炎とは症状が少し異なっています。このような「ちょっと変わった肺炎」のことを「非定型肺炎(または異型肺炎)」と呼びます。
この非定型肺炎を理解するためには、まず定型肺炎を知る必要があります。昔(例えば1900年頃)、肺炎と言えば肺炎球菌による肺炎でした。高齢者に多く、聴診で明らかな異常音があり、胸部レントゲンでは広い浸潤影(真っ白な影)を認め、生命に関わるような重篤な病気でした。このような定型肺炎では血液検査をすると白血球数が上昇しており、患者の痰を顕微鏡で観察すると菌を見ることが出来ました。
しかし1930年代ごろから、若年者に一風変わった比較的軽症の肺炎が存在することが報告されるようになりました。これらの特徴は下記のようなものです(発熱や咳などの症状があり、胸部レントゲンで異常があることが前提です)。
- 60歳以下の若年者に多い(特に思春期)
- 基礎疾患がないか、あっても軽い
- 頑固な咳がある
- 聴診器で異常音が聞き取りにくい
- 痰がないか、あっても顕微鏡検査で病原菌が見つからない
- 血液検査で白血球数が正常範囲内にある
このような特徴を持つ肺炎は非定型肺炎、ないし異型肺炎と呼ばれるようになり、やがてその原因がマイコプラズマ・クラミジア・レジオネラ・一部のウイルスなどであることが判明しました。
現在では非定型肺炎の大半はマイコプラズマ肺炎であることが明らかになっています。特にマイコプラズマの流行期に非定型肺炎を認めたなら、追加検査なしでマイコプラズマ肺炎と診断しても大きな問題はないと考えられています。
このような診断方法は簡便かつ実践的ですが、マイコプラズマの存在を証明したわけではないので、万が一マイコプラズマ肺炎ではなかった場合に治療が後手に回ってしまう可能性もあります。
8.マイコプラズマの治療
日本におけるガイドライン「肺炎マイコプラズマ肺炎に対する治療指針」では、マクロライド系抗生剤をまず使用するように推奨しています。
ただし、ここに悩ましい問題があります。マクロライド耐性菌の問題です。
もともとマイコプラズマに効果のある抗菌薬はマクロライド系、ニューキノロン系、テトラサイクリン系の3つにわけることができます。
このうち、マクロライド系抗生剤はマイコプラズマに対する効果が高く(最小発育阻止濃度/予測される組織中の濃度が低い)治療終了時には気道からマイコプラズマを完全に取り除くことが出来ます。
一方、ニューキノロン系、テトラサイクリン系の効果はそれよりも低く、また一部の症例では治療終了後も気道にマイコプラズマが少し残ってしまうことが知られています。
したがって昔は何も考えずにマクロライド系抗生剤を使えば良かったわけです。
しかし2000年頃からマクロライド耐性マイコプラズマ(マクロライド系の抗生剤が効かない!)が流行するようになりました。その割合は徐々に増加し、2011~2012年にマイコプラズマが流行した際には、なんと約80%ものマイコプラズマがマクロライド耐性となっていました。
その後、徐々にマクロライド耐性率は低下し、現在の日本国内における耐性化率は20~30%ほどと見積もられています(実はマイコプラズマ・ニューモニエは1型と2型に分けられるのですが、マクロライド耐性株は1型で多く2型で低いという特徴があります。現在は1型の割合が下がり2型が増えているため耐性菌の割合が減っています)。
ただし東アジアでは中国で90%以上、韓国で80%以上、台湾で70%以上のマクロライド耐性化率が報告されています。これだけ国境を越えた人の移動が活発になっている現在、このまま日本の耐性化率が低いまま推移すると考えるのは楽観的すぎるように思います。また、国内の耐性化率には地域差があり、耐性菌が多い場所では60%を越えると言われています。
さて、そこで質問です。効果は高いが4~5人に1人の割合で効かない抗生剤と、効果はやや劣るがほぼ全員に効く抗生剤、みなさんならどちらを使って欲しいですか?
ガイドラインではまずマクロライド系抗生剤を使用することになっています。48時間以内に熱が下がらなければマクロライド耐性と考え、ニューキノロン系かテトラサイクリン系に変更することと定められています。
ただ、マイコプラズマ肺炎は高齢者の肺炎球菌肺炎と比較すると症状は軽いものの、それなりに強い倦怠感や39度近い熱、頑固な咳などが持続する疾患です。4~5人に1人の割合で効かない抗生剤を第一選択とすることが本当に正しいのか、現場の医者としては判断に悩むところです。
この問題の解決方法は治療開始前にマクロライド耐性菌の存在を調べ、それによって薬剤を選択することしかありません。現状でこれが可能な検査はPCR検査のうちQプローブ法のみになります。
逆に中国のようにほとんどが耐性菌になってしまえば、マクロライドを完全に選択肢から外すことになるので悩むこともなくなるのですが、、、
将来的には2剤以上の抗生剤の併用がマイコプラズマ肺炎に対する標準治療になるのかもしれません。
